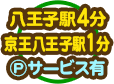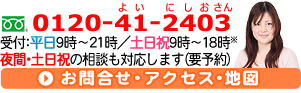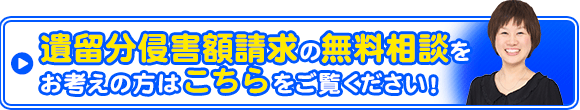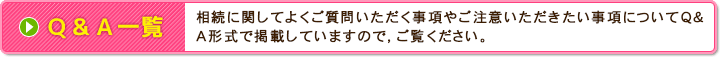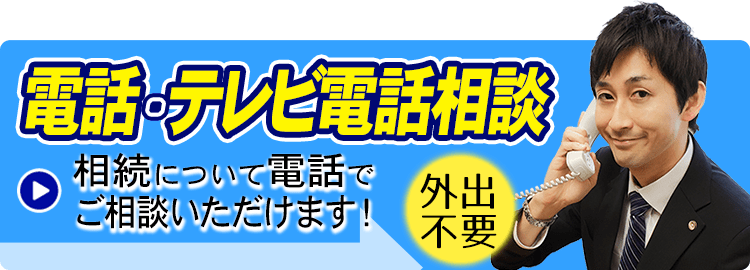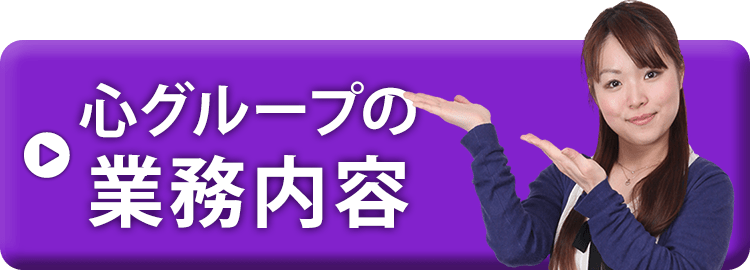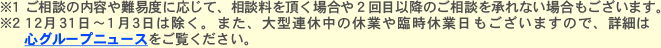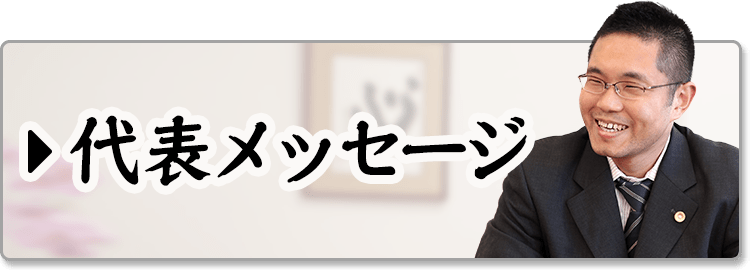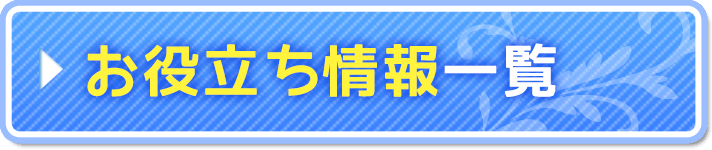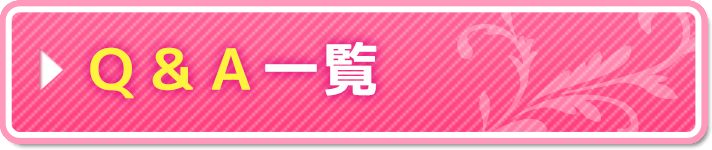遺留分と法定相続分の違い
1 遺留分と法定相続分は何が違うのか
遺留分と法定相続分は、相続の場合に問題となる点は同じですが、主張できる権利者や割合などが異なります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分をいいます。
たとえば、法定相続人が長男と次男の2人で、遺言ですべての財産を長男が取得した場合に、何ももらえなかった次男が長男に対し、遺留分4分の1を請求することができます。
これに対し、法定相続分は、遺産を相続する場合の相続割合をいいます。
遺産分割協議の際に、法定相続人が長男と次男の2人であれば法定相続分はそれぞれ2分の1であるため、協議において、長男が次男に対しすべての遺産を取得したいと主張したとしても、次男は法定相続分2分の1を主張することができます。
2 権利者の違い
法定相続分を有する法定相続人は、配偶者が常に相続人となるほか、子(いない場合は孫)、子がいない場合は直系尊属(父母、祖父母など)、子や直系尊属がいない場合は兄弟姉妹となります。
これに対し、遺留分を有する遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人であり、配偶者、子(いない場合は孫)、直系尊属(父母、祖父母など)となります。
たとえば、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹であった場合、遺言により配偶者がすべて取得すると、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に対し請求することができません。
3 割合の違い
遺留分の割合は、基本的に法定相続分の2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は、3分の1となります。
相続放棄する場合の遺品整理について マンションを相続した場合の手続き